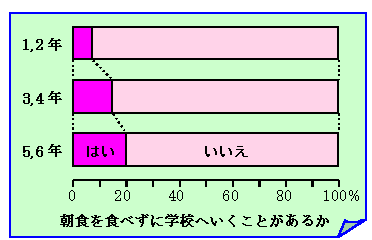
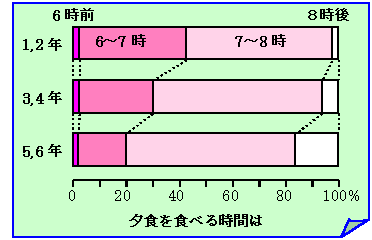
ニュータウンあれこれ
子育てをしている親にとって、自分の子供が周りの子供たちと比べてどうなんだということは、気になるところです。それは、勉強のよしあしだけでなく、生活全般にわたってのことでもあります。そこで、ニュータウン内の小学校で行われたアンケートの結果を元に、この近隣における、いまどきの小学生の生活の様子をまとめてみました。
(’00年1月作成)
まずは、食生活とテレビについてのアンケート結果についてです。朝、学校へ行く前に朝食をちゃんととっているか、また夕食を何時頃に取っているかの結果を下図に示します。
学年が進むほど朝食を抜くことがある子の割合は増え、高学年では2割に達しています。さすがに、毎朝食べていないという子は数%以下でしたが、ときどき抜く子は少なくありません。夜寝る時間が遅かったりして、登校時間ぎりぎりに起きるため、朝食を食べる時間が取れないというのが、理由の一つのようです。でも、ニュータウン地区の小学校の通学区域はそれほど広くなく、1時間も通学にかかることはまずありません。午前の授業中にボーっとしている子供は、朝食を抜いていることが多いとも言われていますので、朝はちゃんと食事がとれる時間に起こしたいものです。それでも間に合いそうもなければ、バナナ半分をかじらせるだけでも、だいぶ違うようです。
次は夕食の時間です。これも、学年が増えると遅くなる傾向にありますが、だいたいは6〜8時というのが大半です。さすがに、8時を過ぎてという場合は、親の仕事の都合や塾通いの時間帯などが関係しているようです。
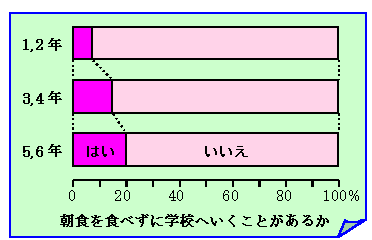
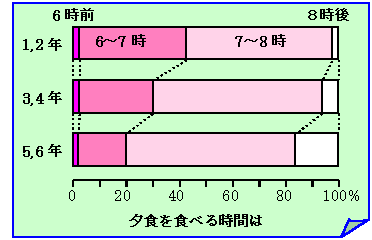
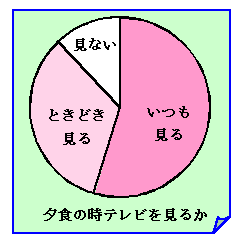 そうなると気になることは、ちょうと子供向けのアニメ番組などのテレビの放送時間帯と重なっていることです。そこで夕食を食べながらテレビを見ているかどうかを聞いてみました。 左図の結果を見ると、かなりの割合で「ながら族」になっていることがわかります。これらの中には、家族と一緒でなく子供だけで食事をする場合がかなり含まれているようです。食事の時間というのは、子供と親のコミュニケーションをとることのできる、大切な時間の一つだと思います。その日の学校での出来事を話しながら、または手作りの料理を味わいながら、楽しいひとときを過ごしたいものです。テレビを見ながらでは、どんな料理を食べてもほとんど記憶には残りません。また、食べたものの消化にもよくありません。仕事の帰りが遅く、親の食事時間とずれてしまうため、子供だけの食事にならざるを得ない家庭も多いでしょう。でも、一緒に食べられないまでも、だれか大人が同じ食卓に座っていることだけでも十分だと思います。我が家の子供たちは、どうしても見たいテレビ番組がある場合、しっかりとビデオの録画予約をするという技を身につけたようです。 |
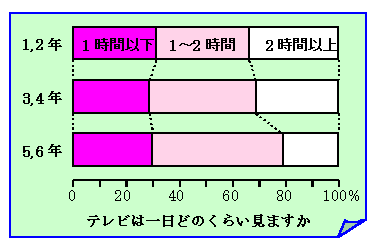 それでは、一日にテレビを見る時間はどれくらいあるのでしょうか。 結果は左図のように、平均2時間程度とあまり多くはありませんでした。でも、これは放送番組を見た時間であって、テレビそのものを見ている時間ではありません。実は、これ以外に今の子供たちはテレビゲームで遊んでいる時間がかなりあり、実質的にはこの倍以上テレビ画面と向き合っているわけです。高学年になって、あたかもテレビを見る時間が減っているような結果も、テレビゲームで遊ぶ時間がそれに反して増えたためだとわかります。 さらに近い将来、パソコン文化が子供たちにも広まるようになると、もっともっとテレビ画面を見る時間が増えていくことが考えられます。一時期話題になったテレビから出る電磁波が健康に与える影響の心配は、だいぶ軽減されたようです。でも、画面に張りつくようにしてゲームをしている子供たちの、視力への影響は無視できないようにも思われます。塾へ行く電車の中でもゲーム機の画面に張りついている子供たちを見ると、ちょっと心配になってしまいます。 |
どうしようかと悩むことの一つに、おこずかいがあります。親の自分たちが育った時代とは、あまりにも異なる経済的な環境にあるため、どの程度が適当なのか検討がつきません。そこで、決まったおこずかいをもらっているか、どの程度の額をもらっているかを聞いた結果が下図です。
学年上がると大多数が、決まったおこずかいをもらうようになるようです。また、おこずかいをあげている家の8割近くが、子供にこずかい帳をつけさせているという結果もあります。こずかいによって、ある程度の金銭感覚を身につけてもらおうという、親の期待が現れています。
こずかいの金額は、月に500円から1000円程度が平均のようです。でもこれでは、本当にほしいような遊び道具を買うことはできません。テレビゲームのソフトは中古でも数千円、発売直後では1万円近くします。このような高額のおもちゃは、誕生日やクリスマスのプレゼントとして、あるいはなにかのごほうびとして、こずかいとは別に買い与えているようです。また、お年玉も数千円単位で両親や、祖父母からもらっていますので、それで買うこともあるのでしょう。
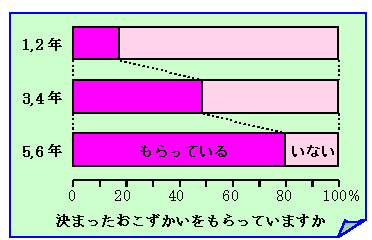
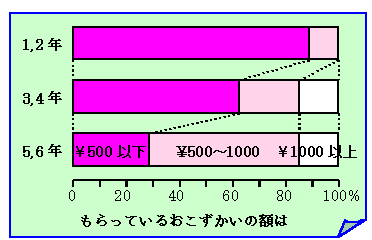
友達とよく遊ぶか、休日に家族と遊ぶか聞いた結果が下図です。
低学年でも友達と遊ぶのは6割程度で、学年が上がるとさらに少なくなっていきます。あとで示すように、塾や習い事に通う割合が増えて、友達と遊ぶ時間がなくなっていることもあります。また、テレビゲームは一人でも楽しめるため、わざわざ友達と遊ぶ必要がないことも理由の一つでしょうか。昔のガキ大将を中心とした子供社会は、今ではもう見られないものなのかもしれません。
では、家族とは遊ぶかというと、さすがに友達よりは割合が高くなっています。それでも、高学年で半分程度ですから、友達とも家族ともほとんど遊ばないという子供がかなりの割合でいることになります。最近の若い人は、人づきあいがあまりうまくないという原因の一つとして、普段からのまわりの人たちとのコミュニケーション不足が言われていますが、この結果からもその一端をうかがい知ることができるようです。
でも、同じ時期に母親を対象に行ったアンケート結果を見ると、母親同士の人間関係で悩んだことがある人が半分近くもいることがわかります。「公園デビュー」ということばも作られたように、自分の生まれ育った所とは違う環境で、孤独な子育てをしいられている母親も、コミュニケーションの壁にぶつかっていることがわかります。そして、それが子供の人つきあいにも反映されてしまっているのです。子育て中の母親が、気兼ねなく人づきあいが出来るような場が、もっと身近に増えてほしいと思います。
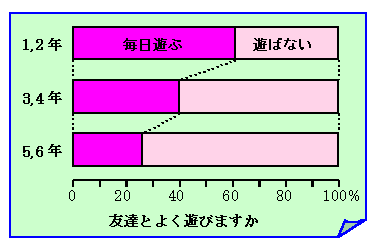
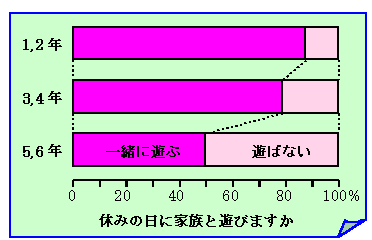
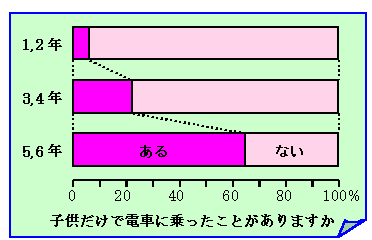 遊びばかりが目的ではないでしょうが、どれほど親離れしているかという目安として、子供だけで電車に乗ってどこかへ出かけたことがあるかどうかを聞いてみた結果が右図です。 |
学習塾や習い事などにどの程度通っているかのアンケート結果が下図です。
高学年では、半数の子供たちが学習塾に通っています。目的は補習と受験とが半分づつくらいでしょうか。一割強の子供たちは、3,4年のころから受験を目指して塾通いをしていることもわかります。全国規模の調査では、高学年で40%程度が平均値のようですから、すこし高めではあってもそれほど突出した数字ではないようです。ちなみに公立小学校から、地元の公立ではなく、私立の中学校へ進学する割合は、20〜30%程度が最近の地域の状況です。
一方、習い事については、学年にはあまり関係なく、60%ちょっとの数字になっています。男女別で見ると、各学年とも女子の方が20%ほど男子より高い数字になります。また、内容については、女子はピアノやエレークトンなどの音楽系とバレーなど、男子はスイミングやサッカー、野球などのスポーツ系が多くなっています。この結果を見ると、高学年では学習塾も習い事も両方通っている子供がかなりいることがわかります。毎日のようにあちこちに通う生活では、友達との遊び時間が取れないのも当然の結果なのかもしれません。
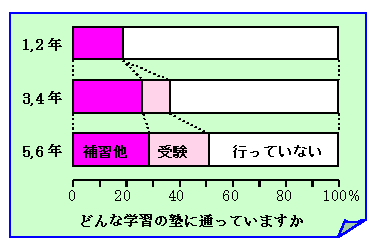
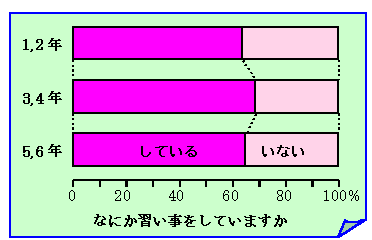
それでは、子供たちは自宅にいるとき、どこで勉強をしているのでしょうか。 |
いくつかの調査結果から、今の子供たちのようすを描いてみました。親の私たちとはまるで違った生活環境で育っていることが、あらためてよくわかります。親自身のとまどいや不安が、そのまま子供の態度に反映してしまうこともあると思います。まわりの環境を理解することが、少しでもみなさんの子育ての参考となれば幸いです。
第9話へ<<= 第10話