|

都筑大介 ひなたやま徒然草 7
平成十七年正月
新年を言祝(ことほ)ぎたい
ひなたやまは真っ白な雪に覆われた美しい正月だった。二十一年ぶりらしい。
「らしい」と言ったのは、ボクがここに引越して来たのがちょうど二十年前である。だから、当然その前のことは知らない。しかし、知らないというのは好いもので、実に新鮮な正月の風情を味わわせてもらった。
といっても自分がしていたことはいつもの年と変わらない。女房殿に「新年おめでとう。今年もよろしく頼むよ!」と軽く会釈をし、「お父さん。明けましておめでとうございます」とうやうやしく挨拶する愛娘に「うん、おめでとう!」と鷹揚に答えて父親の威厳を示し、その後は「雪見酒てぇのはオツなもんだねッ」とほざきながら朝から酒浸りだ。午前十時すぎには早くも沈没して、午後五時近くまでぐっすりと熟睡した。それなのに夜は早々に眠くなって、「俺も体力が落ちたのかなあ」とぼやきながら早めに床に就く始末。ああ、情けない。
二日も朝から飲んだくれて、三日も同じように過ごして、ようやく今日四日の朝にボクは現世に復帰した。
元旦に酔眼でさっと目を通して机の上に放ってあった年賀状を、今朝ようやく一枚一枚丁寧に読んだ。
「バカなお前を見捨てもせずに年賀状をくださったというのに、お前はなんという罰当たりなんだ!」と自嘲しつつも、印刷された年賀文の脇に添えられた手書きの短い文章を目にすると自然に頬がゆるむ。先輩・後輩・友人の皆さんが本当にボクのことを気にかけてくださっている。それが嬉しい。心が温まった。
ところで、年賀状というのは「つつがなく迎えた新しい春を言祝(ことほ)ぎ、その心を伝えようとするもの」である。この風習がいつ頃からはじまったのか正確には知らないが、どうやら江戸時代よりうんと前に遡るらしい。そして、旧くは年が改まってから出すのが普通であったという。
それが明治時代の後半に、迎えた新しい年を祝うはずの手紙を前の年の暮れのうちに書いて投函するという――しかも国レベルで一斉に行うという特殊な――現在のスタイルに変わった。
明治三十二年(1899)、政府は郵便法に年賀状だけは特別な取り扱いをすることを定めた。つまり、元旦の朝の年賀状配達は郵便局のサービスではなく、郵便法第67条に定められた郵便局の義務行為なのである。
だから郵便配達の人に「ご苦労さま。ありがとう」なんて声はかけなくてもいい、とボクは言っているのではない。ボクが気にしているのは、年賀状を出すことが国民の義務であるかのように国が誘導してきたことである。
明治三十二年というのは大日本帝国憲法が発布されて十年目の年にあたり、朝鮮の支配権をめぐって清国と争った日清戦争(1894〜1895)と満州と朝鮮の支配権をめぐって帝政ロシアと争った日露戦争(1904〜1905)とのはざまにあって、「富国強兵」が叫ばれる中で大日本帝国は膨大な軍費を必要としていた頃である。国民がこぞって年賀状を出せば、国の収入は莫大になる。
ついでにもう一つ。厚生年金は太平洋戦争最中の昭和十七年(1942)に工場労働者を対象とする労働者年金として発足し、二年後に厚生年金と改称して加入者の対象を事務職員や女性にまで広げた。老後を保障してやるから皆してせっせと年金保険料を納めろという訳である。給料から天引きする制度もこの時に生まれた。
こう説明すれば賢明なる諸兄諸姉にはすでにそのカラクリがお分かりと思う。
年賀状を交わして旧交を温めることは良いことだし、安心して暮らせる老後のために保険料を払うのも致し方ないことだ。
しかし……と、ボクは考え込まされてしまう。
つまり、制度発足の「動機が不純」なのだ。
そして、不純な動機で成り立ったシステムだからだろう、今の政治家と官僚は屁理屈を編み出していとも簡単に改定してしまう。いや、改悪してしまう。それが将来ビジョンを示せない政治と財政が破綻しそうになると増税すればいいと思っている行政の真の姿ではなかろうか。
ボクには、国民の我慢も限界に近づいてきているように思えるのだが、「ヨン様」とやらを追いかけて亭主を顧みず、刹那的に生きている能天気なオバハンたちにも選挙権があるから始末が悪い。
この国は、この先一体どうなっちまうんだろうか?
ボクたち庶民が心のの底から新年を言祝げるのは、一体いつになるのだろうか?
願わくば、ボクが生きているうちにそうなって欲しいものである。
[平成十七年一月]
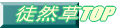
|