青春譜 4
友の情は白 |
 |
三月初旬。寒さはまだ和らいでいない。
俺たちはつい二時間ほど前に、最後のコンサートの舞台を下りた。
成功を祝ってくれた多くの友人たちにお礼の挨拶を述べ、他のバンドメンバーとも別れて、二人きりで飲み明かすつもりで、タクシーを拾ってアイツの家へ向かった。
この日、俺とアイツで作り上げたロックバンドは解散した。
俺たちは皆、プロを目指す道を捨て、揃ってサラリーマンになることを選んだ。あと二週間もすれば俺は長髪を切って上京する。
普段無口なアイツが、タクシーの中で珍しく饒舌(じょうぜつ)だった。
四月の末に貰う初任給の三倍もするギターがどうしても欲しくて衝動買いをし、組んだローンが払えなくてやった夜勤の土方仕事にバスの車掌、練習場を探す苦労、新譜レコードから譜面を起こす徹夜作業、一日八時間も歌い続けて喉を潰してしまったこと……。
そんな想い出をなぞりながら、興奮さめやらぬ彼はしゃべり続けた。
俺は、というと……。
妙に冷めていて、聞き役に徹した。いつもと役割が逆になっていた。
繁華街の中央を南北に貫いている県道を北へ向かい、市街地を通り抜けた辺りから西へ走り、川に突き当たったところで堤防沿いに再び北上した。
俺が初めての東京で多分目を白黒させている頃には、間違いなく夜桜見物の酔っ払いで埋まるのがこの河原だ。
まだ固い蕾を横目に見ながらくねくね伸びる道を十分ほど行って右に折れ、小さな坂を登り、その坂を降ったところに彼の家はある。
時計の針が午前零時を少し回った頃にタクシーの運転手はブレーキを踏み込んだ。
アイツは母親と二人でその市営住宅に住んでいた。
が、その家に灯りは点っていない。ここから車で二時間ほどの町に住んでいるアイツの兄貴に赤ん坊が出来て、母親は昨日から初孫の面倒を見に出かけていた。
母親は彼がバンドを組んで音楽活動をすることを嫌っていた。だから、最後のコンサートも聴きに来てはくれなかった。
「しようがないよな、俺は兄貴と違って親不孝者だから……」
コンサートの前日に投げやりな口調でアイツがそう呟いた。
「お前はそれでもまだ幸せな方だぜ。俺なんか文句を言ってくれる親がいねーんだから」
確か、その時俺はそう言葉を返した。
俺たちは真っ暗な玄関に足を踏み入れた。
「ただいま!」
「お邪魔します!」
暗闇に向かってひと声ずつ張り上げて、冷えた玄関の板敷きに上がった。
手探りで電灯のスイッチを入れる。
つい先ほどまで玉の汗が噴出す強烈な舞台照明の中にいた二人にとって、蛍光灯の光はくすんでいてなんだか心許ない。
ブルブルッと身震いをしたアイツはストーブに火を入れた。
「なんだか侘(わび)しいけど、邪魔がいねーから、いいやなっ」
苦笑いするアイツに笑顔を返した俺は、卓袱台を挟んでアイツと向かい合い、胡坐を組んだ。そして、部屋中にタバコの煙を立ち込めさせながらよく飲んだ、アイツも俺も……。
卒業前の最後のイベントをやり遂げた安堵感と解放感に、俺たちは浸った。
しかし、酒がすすむにつれて高揚感は寂しさに変わって行った。互いの顔を見つめては深いため息を吐いた。
アイツは頬を引き攣らせて笑った。泣いているような笑顔だった。
「外を歩いてみないか」
そう俺が誘った時、時計の針は午前三時を指していた。
月は出ていなかった。
薄い霧が冷たく立ち込める中にポツンポツンと街頭が佇んでいる。
かろうじて判別できる道は、夜の闇が足元から立ち昇っている。足を止めるとその闇の底に吸い込まれそうな気がした。
ぼんやり霞んでいる街頭を頼りに俺たちは肩を組んでヨロヨロと、右に左に千鳥足を踏んで河原へ向かった。
声を張り上げて歌った、音階もメロディも滅茶苦茶に……。
二人とも呂律(ろれつ)が回らないほど酔っていた。
ワイシャツの前をはだけた互いの姿に改めて気づき、歌うのをやめて笑った。
冷気が体に凍みてきて、熱く膨らんでいた頭が少しだけシャンとした。
河原に辿り着くと空から舞い降りてきたものが冷たく頬に当たって溶けた。
雪だ……。
俺たちは、ズボンの裾を捲り上げてせせらぎに足を踏み入れた。
刺すように冷たい。滑らかな表面の砂利石が足の裏をくすぐる。
水の流れが単調な旋律を奏でている。
俺たちが確かに生きていることを知らせてくれた。
「面白かったなぁ」
アイツが振り向いてそう言った。
「ああ」
俺はうなずいて水の流れを見つめた。
「もうじきお前は東京に出て、俺はこの町に残る……。俺さぁ、これからも作曲だけは続けるつもりだ、会社勤めの合間に……」
「そうしろよ。お前は俺より音楽の才能があるから。俺はそのうち物書きになろうと思ってる。けど、当分はサラリーマン稼業に精を出すよ。そうしなきゃ喰っていけないから」
「俺もそうさ。これ以上オフクロや兄貴の世話になる訳にゃいかないし、働かなきゃ喰っていけない。中途半端なんだよ俺の才能は。プロにはなりたいよ。でも今すぐそれで喰っていける自信はないしさ……。それに俺、学校を間違ったみたいだ。国立大学を卒業すれば周りは当然いい会社に入って出世することを期待するよな。作曲して歌を歌って生計を立てるなんて誰も賛成してはくれないよ。何のための大学だったんだって、学費の面倒をみてくれた兄貴に、大学を諦めて死んだ親父の代わりをしてくれた兄貴に怒鳴られちゃうよ」
「…………」
「親父が死んだのは俺が中学二年の時だった。兄貴はその時高校三年で大学受験の勉強をしてたんだけど、就職することにしてさ……。俺に、お前だけでも大学へ行ってくれと言われた時は涙が出たよ。金に余裕はないから学費の安い国立大学という条件付だけどな……。だから、高校時代の俺は本当に必死に勉強した。俺、元々あんまり頭のいい方じゃないから大変だったな、家族の期待をヒシヒシ感じてさあ。お前と違ってギリギリの合格さ……。その反動だな、大学に入った途端に勉強する意欲が失せちゃったのは……。授業だってオフクロや兄貴の手前もあって出席してたようなもんでさ、成績はお前も知っての通りにオール可。いつも考えてたよ、自分に向いてないことをやってるって」
「…………」
俺は黙って聞いていた。
「だから、お前と一緒に始めたバンドが楽しかったし、ずっと嬉しかったよ」
「…………」
俺は軽く頷いて暗い川面を見た。
「面白かったよなぁ、この四年間……」
そう問われて俺は口を開いた。
「ああ、色々あったよなぁ。お前、Y先輩を憶えてるか?」
「グリークラブのか?」
「そう。あの人が俺の中学高校時代の仲間の兄貴だってこと、知ってるよな」
「そう聞いたな」
「そのY先輩にキャンパスで出会って勧誘されて、仕方なくグリークラブに入ったらお前がいたんだよ。でも、俺は声が細いせいかバックコーラス専門で、歌っててもちっとも楽しくなかった。二三ヶ月で飽きちゃった。その時だよ、お前が俺にバンドを組んでビートルズを歌わないかって誘ったのは……」
「そうだったか……」
「そうなんだ。それからメンバーを集めて、バイトして楽器買って、夏休みの教室借りて喉を潰したのは……」
「そうだったなぁ」
「猫も杓子(しゃくし)もベンチャーズの頃だったから、ボーカルやる俺たちは異色の存在だった。ま、俺とお前が歌ってんだからお世辞にも上手いとは言えないけど……。なのに、すぐに有名になっちまって、暮れのクリスマスはダンスパーティの連続で、ずいぶん稼いだよな。楽器のローンも半分払ったし、結構裕福な暮らしが出来る金が手元にあった、お前が『もっといいギターに買い換えようよ』とさえ言わなきゃな」
「そんなこともあったな。あの時、ディスコクラブの出演が決まったろ? それで俺はそうしたいと思ったんだ」
「俺も、ポール・マッカートニーが使ってたバイオリンタイプのエレキベースが欲しかったから、二つ返事で賛成して貧乏生活に逆戻りさ。夜中の土方はキツかったよ、寒くて……。バスの車掌は眠かったな、いつも始発に乗らされてたから……。家庭教師も続けてたからずいぶんと忙しかった、あの頃は……」
「二人ともよく単位を落とさなかったよな、ろくすっぽ授業にでてなかったのに」
「ああ、そればかりはSのお陰だな。生真面目なSがとった講義ノートの……」
「その代わり、あいつの飲み代はいつも全部俺たちが払う羽目になった……」
アハハハハハハ……。
笑い声が弾けた。春の雪は人目を忍ぶようにひっそりと、そしてふんわりと、二人を包んで降り続いた。
東の空が白み、小鳥の羽音とさえずりが聞こえ始めた。
遠くのあちこちで車のエンジンを始動させる音が聞こえたと思うと、濡れた路面を疾走する音が次第に高くなってきた。つい先ほどまで耳元に迫っていたせせらぎの水音が遠ざかっていた。
俺たちはもう一度せせらぎに足を踏み入れた。
素足にぶつかる水が冷たい。吐く息の白さが驚くほど鮮やかだ。
瞬く間に夜が明けていく。
新しい一日がもう始まっていた。
互いの全身を炎のように熱い何かが瞬時にすり抜けた。
俺とアイツは青春の一ページを閉じた。
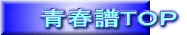
|