|
都筑大介 ぐうたら備ん忘録
その参 幻想の効用
久し振りに……、本当に久々に、筆をとる。
三年前、この雑文を書き始めてすぐにボクは筆をおいた。まったく文章が書けなくなったからである。考えることが苦痛になり、人に会うのが怖くなった。散歩に出かけることすら億劫になり、まさに“引き籠もり中年”になってしまった。
そして一年経ち、二年が過ぎ、三年の時が流れ、あれから三度目の年の瀬を迎えて、ようやくボクは、何か書いてみようという気持ちになれた。
今年の夏の終わりにボクはある精神分析家に出遭った。フロイド心理学をベースに独自の理論を展開している『岸田秀』である。といっても彼の著作に巡り会っただけなのだが、ボクは、ボクよりひと廻り年上のこの心理学者のお陰で、今まで見えていなかった自分自身のことが、少し見えるようになった。
最初に手にした彼の著作は、映画監督でもあり俳優でもあった故伊丹十三さんとの対談を収めた、『哺育器の中の大人たち』だった。
ちなみにうちの女房殿は伊丹夫人の宮本信子さんに似ている。
ちなんでないか? ま、余り深く考えるのはよそう……。それはさておいて、ボクはこの本の中で“史的唯幻論”なる耳慣れない理論に遭遇した。
岸田は言う、「我々人間は現実そのものを有りのままに見ているということは絶対にない、どんな場合でも我々自身の“幻想”を介して見ている、常に何かの“意味”を貼りつけて見ているのだ」と……。そして、こう説明していた。
「他の哺乳類は発達してから生まれてくるわけですね。だから、生まれて少しすれば自分で歩いて、自分で食べ物を見つけて自活できるわけです、彼らは何が食べられて何が食べられないかを本能で知っているわけですから。ところが人間の場合、そういう本能が生まれた時にもう壊れている。いや、壊れていると言うより未発達なんだなぁ。本来なら胎内で発達して完成すべきだったのに、未完成な状態で放り出されるわけです。人間の場合はですね、親が、食べられるものを与えて、子供にとって人工的な環境を作ってやらなきゃいけないわけです」
岸田は、人間はみんな未成熟な状態で生まれてくる、家庭が大きな哺育器(ほいくき)である、未熟児ゆえに現実を遮断した哺育器の中でしか人間は育ち得ない、と言う。確かに人間の赤ん坊は親や周囲の誰かが世話をしてやらなければいとも簡単に命を失う。意味あいは多少違うが、ごく最近、パチンコ好きな母親が車の中に赤ん坊を置き去りにして死に至らしめるという悲惨な出来事があった。そのことがボクの頭をよぎった。
岸田はさらにこう述べている。
『幻想』は生まれた時にすでに持っているわけではない、赤ん坊として周囲の世界との経験の過程で一つ一つの幻想を持ってゆくのだ、と……。周囲の世界が赤ん坊に“幻想”を与え、赤ん坊はその幻想を身に着けて周囲の世界に適応していく、本能の未発達な部分を幻想で補っていく、ということらしい。
「動物の場合は本能によって規定された現実の意味に従って行動し適応してるんです。人間は本能が壊れてるから、本能に規定された現実世界の意味構造を失ってるもんだから、生まれたあとに行動規範を勝手につくるわけですよ。規定されてないんだから勝手につくらざるを得ない。その勝手につくったものを僕は幻想と呼ぶわけですね。我々人間が住んでいるのは意味の世界なんです」
本能によらない現実の意味を貼りつけた行動規範の中心が“自我”である、と岸田は論を展開していた。
フロイドは個人の精神を、超自我(無意識的良心)・自我(現実を知覚し判断するもの)・エス(自己の一部であり本能と衝動の貯蔵庫)の三つに別けているが、岸田は、「少々乱暴な別け方だが」と断って、「善悪を判断するのが超自我、損得を考えるのが自我、快不快を感じるのがエス」だと考えればよい、と分かり易く解説している。その損得を考える自我が幻想をつくる、ということらしい。
さらに、「現実は一つしかないわけだけど、誰でも皆、自分が今見てるところのものを現実だと思ってる。だけど、各々が現実だと思ってるものはお互いに食い違っていて矛盾さえしてるわけでね。そんなに色々な現実なんてありっこないんで、これは幻想ではないかと……」と、彼が史的唯幻論を標榜するに至った端緒に触れて、「敗戦の時、今まで大人を動かしてた何かの価値が一朝にして崩れて、で、価値が変わると大人の言動もすべて変わってしまった」と、集団の抱く共同幻想にも言及している。
「人間は、幻想として抱く“理念”や“価値”や“正義”のために、使命感に燃えて真剣に戦うという愚劣極まりない行為を繰り返してきた」わけだから、その行為自体を根絶すべきだと岸田は述べる。そう述べた後で、「お互い幻想を貼りつけてるから、人間関係、不必要な諍いとか、色々問題が起こるわけなんでね。しかし、だからといってね、幻想なくして人間関係、可能かどうかなんですよねぇ」と首を傾げていた。
「ところでお前、岸田秀の言ってることがすべて理解できたのか?」
そう問われると、正直なところボクは返事に窮する。が、明らかにボクの心は共鳴していた。とりわけ共感を覚えたのは日本人の精神構造を分析した下りだった。それは概ね次のような内容である。
《アメリカ人の場合は、建国の父たちが先住民のインディアンを卑劣なやり方で虐殺した。その最初の虐殺経験を正当化したために、正当化を自己強迫的に繰り返さざるを得なくなって正義と暴力が結びついた。それで、異民族のところへ乗り込んでは“正義という立場”でその民族を滅ぼす。そういう正当化された愚劣な行為を繰り返す“自立した力の自我”をアメリカ人は持っている。一方、日本人は、本来自分は攻撃を好まない温和(おとな)しい平和的な人間だというセルフイメージがあるから、力による攻撃を悪い事だと視る。だから、我慢に我慢を重ねてこれは止むを得なかったのだという状況をつくって、自分の攻撃性を相手の悪によって正当化する“他律的な自我”を持つ。つまり、精神分裂症患者と同じである。日本人が歴史の上で180度くるりと方向転換した例は枚挙に暇がない。例えば、黒船来襲で攘夷の機運が最も高まった時に開国し、鬼畜米英の掛け声は戦争が終わるとマッカーサー万歳に変わった。自己が正反対の二つの極に分裂していて、その都度どちらかが出てくる。純粋・自尊・過激の“内的自己”が自我の中心を占めたり、妥協・適応・需要の“外的自己”が自我の中心になったりする。往々にして内的自己は抑圧され、抑圧されても存在しているから、いつかは爆発する。内的自己も外的自己も共に自己なのだということを認めて自己の統一を図らなければ分裂は治らない》
ボクは、ひどく感心し、いたく刺激を受けた。ボク自身にも岸田の言う日本人的分裂症状がある。いや、あると気づかされた。ボクはパソコンの前に座り、インターネット古書店を訪ね歩いて、彼の著作を買い漁った。
「ものぐさ精神分析」から読み始め、「続ものぐさ精神分析」「二番煎じものぐさ精神分析」「出がらしものぐさ精神分析」「ものぐさ箸やすめ」「ふき寄せ雑文集」「不惑の雑考」「フロイドを読む」「幻想を語る」「さらに幻想を語る」「幻想の未来」「希望の原理」「自我の行方」「嫉妬の時代」「倒錯」「浮遊する殺意」「心はなぜ苦しむのか」「日本人の不安を精神分析する」などなど、手当たり次第にむさぼった。
ついでにと言っては失礼になるが、ついでに……。河合隼雄・小此木啓吾・佐々木孝次・土居健郎・多田富雄・養老孟司といった方々の“心と脳”に関する著作も買い集めて読んだ。
結局ボクは、三ヶ月余りの間に三十冊を超える専門書を読破した。
元々ボクは本が好きで、読み始めるとやめられず、明け方になるのはしょっちゅうだった。会社勤めの頃はよく徹夜の読書をしてしまい、会社で居眠りをしては上司から叱られた。その頃のボクは、必要に迫られてビジネス関連の本も沢山読んだが、普段読むのはほとんどが小説で、特に山本周五郎や司馬遼太郎や池波正太郎の時代物を好んだ。最近は少し趣の違う京極夏彦の伝奇ミステリーに嵌っていた。だから、心理学とか精神分析とかの難しくて頭が痛くなりそうな本を短期間にこれほど大量に読んだのは初めてだった。それほど心惹かれていた、なかでも岸田秀の著作の中の彼の“ものの見方・考え方”に……。蛇足になるが、敢えてその幾つかをここに紹介しておきたい。
《人間は、価値のない人生は生きるに値しないという根強い先入観を抱いている。それ故に、自分の存在に何の価値もないという虚しさは耐え難い。不安でもある。しかし、価値とは幻想に過ぎない。人間は、価値が無く生き甲斐がなくても生きることを学ばなくてはならない》
《人間は、誰だって死ぬのは怖いし、本来的には臆病なのだ。それが勇敢であるのは無理して頑張っているのであって、そこには無理をしなければならない可哀相な事情がある。人間が勇敢であることは、決して褒め称えるべきことではなく、同情すべき哀れなことである》
《人間は、必ずしも危険なこと・苦痛なこと・不幸なこと・嫌なこと好ましくないことだけを恐れるわけではない。何の害もないことでも、自我に組み込めないこと・自我の安定を乱すもの・自我を崩壊させる危険のあるものを恐れる。ひとえに自我の安定が問題なのだ》
《個人が個人として存在しうるためには、“自分についての物語”を持つことが必要かつ不可欠になる。生きるのにも死ぬのにも物語は必要なのだ。自殺をするためには、自殺を正当化するような、自殺する自分の周りの世界における位置を明らかにするような、何らかの物語が必要になる》
《親の心、子知らずというが、実は、子の心を親は知らない。そして、親の心を親自身が知らない。何事にも限界があり、その限界を隠さない愛情こそ本物の愛情である。無私・無条件を装う愛情は偽りの愛情にほかならない》
《自己分析というのはどれだけ自分で自分の逃げ道を塞いでいくかということだ》
《事実を有りのまま書くというのは嘘である。人間にそんなことは出来ない。これから事実を有りのままに書こうと思った時に人間はすでに自己欺瞞に陥っている》
三年前の秋、ボクはかけがえの無い息子を亡くした。妻は己の分身を失い、娘は敬愛する兄を奪われた。平成十年十月九日午後一時三十七分。息子は自らおのが命を絶ち、まだ二十五年と二百八十七日の短い人生の幕を引いた。前の日から降り続いていた雨が明け方に上がり、空が澄みわたって高く抜けた日だった。
それから三年余りの時を隔てた今、ボクはやっと、息子は貴重な土産(みやげ)を置いていってくれたと考えられるようになった。
「人が死ぬいうんはのう……。そりゃ哀しゅうて切のうて……、口に出しちゃあ言えせんがね。死んだんが肉親じゃったら尚更よね。ほいじゃがのう……、涙を枯らして悲しんで、苦しんで苦しんで、苦しみ抜いたんが良(え)かったんじゃろねえ。人を愛するいう気持ちが強うなっとります」
遠い昔、ボクがまだ大学生の頃に耳にしたことのある、被爆老人の言葉が今改めて思い出され、胸に沁みる。
残されたボクと妻と娘の“絆”はとても強いものになっている。以前は今ほどではなかったように思う。と言っても、家庭に波風が立っていた訳ではないが、ボクと妻、ボクと子供たちとの関係はどこか滑らかではなかった。仕事にかまけて家庭のことは妻任せにしていたボクは、仙台・名古屋・大阪と、七年半も単身赴任を続け、子供たちの思春期に家を留守にし、それも家族のためだと自分を誤魔化していた。ボクは独り善がりな幻想を抱いて、会社の出先の長として活躍する自分に満足し陶酔し切っていた。
そんなボクの身勝手で傲慢(ごうまん)な眼を、息子は身をもって醒(さ)ましてくれたのだと思う……。
出世など考えずに転勤を拒否していれば、或いは息子を失うことはなかったかも知れない。バカなことをしていたものだ、と、今更ながら痛切に感じている。が、後悔は先に立たない。
岸田唯幻論に出遭ってから、ボクは過去の自分の行動を客観的になぞってみた。その折々の心理を分析し、善し悪しは別にして、自分の現実であった過去を素直に受けとめる努力をした。まだまだ中途半端だがそれでも筆をとる気持ちになれた。今のボクに何が書けるか見当もつかないが、とにかく、日々身近に感じたことから文章にしていくことにした。いずれ、ボクの心がもっと練れてきて、ボクの筆がヒトの心の様相を的確に描写できるようになったら、ボクはボクの息子のことを一編の小説にしてみたいと思っている。
[平成十三年十二月]
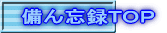
|