都筑大介 ぐうたら備ん忘録
その四 小説を書くということ
『備忘録(びぼうろく)』というのは、あてられた漢字が表している意味の通りに、忘れないための備えとして記録。つまり、移り変わり流れ去っていく季節折々の感慨〔かんがい=身にしみて感じること〕や感動、そして記憶にしまっておきたい事柄などを書き記(しる)しておくことだとボクは解釈している。昔ある時、「人間、やはり大抵のことは忘れてしまう……」という感慨を得た、誰か偉〔えら〕い人が造った言葉に違いない。それにつけても、日々衰えていく脳の記憶力低下に不安を募らせながら、書き残しておこうと何度も思いながら、それがちゃんと実行できない。やはり横着者は哀しい。しかし、ん……。 (俺のって、備忘録じゃなくて『びんぼうろく』なんだから、ま、いいか……)
そう開き直って、二年前にBSE問題に端を発した雪印食品事件を書きとめて以来久々に、この雑文を書くことにした。
「ところで都筑……。お前、この二年余り、何をしておったんだ? どうせ例の横着癖を出してプラプラ遊んでたんだろうが……。おい、どうなんだ? そうならそうと、正直に白状したらどうなんだよっ!」
そう思うよね、誰しも……。
しかし、兄図らんや弟知らんや……。えーと、この古い言い回しは「決してそんなことはないだろうに」という意味の古語「あに図らんや」をもじったオジンギャグ造語なので若い人たちには通じない。従って使用にはくれぐれもご注意のほどを……。戯れはともかくとして、実はその間、ボクは小説を書いておった。平成十三年の暮れに書いた備ん忘録『幻想の効用』の中で触れておいたが、ボクはずっと、亡くした息子のことを題材にした小説を一つ書きたいと思っていた。息子へのレクイエムにしたいという思いに加えて、同じ道を辿る若者が二度と出てこないよう社会に警鐘を鳴らしたいと思ったからだ。
しかし、いざ書き始めてみると小説というのはそうそう簡単に書けるものではない。まだ「ボクの心が練れてきて、ボクの筆がヒトの心の様相を的確に描写できるように」なっていないのだから当然なのだが……。それにしても四苦八苦の連続だった。何度も挫折しそうになった。自堕落〔じだらく=だらしないこと〕な生活が身についてしまうと、根気はとうの昔にどこかへ行ってしまっている。ボクの場合、それを呼び戻すことから始めなければならなかった。
約一年を費やして書き上げたものは四百字詰め原稿用紙に換算して一千枚を超えた。早速知り合いに頼んで編集のプロに眼を通してもらったのだが、「こんなの、小説じゃねーよ」と呆れられたほどまとまりがなくて、やたら長いだけの作品。今振り返ってみると、それがこの段階での正当な評価だったと思う。しかしながら、この時の「小説じゃねーよ」の辛口評価のお陰で、ボクはその後、自分なりに「小説とは何か?」を研究した。蛇足になるかも知れないけど、その研究過程でボクが学んだ小説作法を三つほど挙げておく。
■まず、何よりも大切なことは「何を書きたいのか?」ということ。これがはっきりしていなければ、たとえ良さそうな構想が湧いて来たとしても、物語としてまとめきることができない。つまり、テーマがはっきりしていることが小説に限らず何を書くにしても第一前提となる。それをボクは痛感した。ボクの悪友のひとりが、「自分自身の心の叫びを書くことが大事だと思うよ」とヒントをくれた時には目が醒めた思いがした。ところが当の本人は、「俺、そんなの書いたこともないし、書けねーけどさ」と言ってシャラッとしている。ま、この辺が悪友の悪友たる所以(ゆえん)なのだけど、掛け値なしにありがたかった。また、このことに関連して言うと、「独創(どくそう)性」が大切とのこと。独創性というのは、むつかしく考えないで、自分にしか書けない内容を含んでいることだと思えばいい。それに「普遍(ふへん)性」。これは、読み手との共通のテーマが語られているかどうかが判断基準のようで、それが語られていれば読者の共感を呼び、普遍性を備えたことになるようだ。
■次に、基本的で初歩的なことになるが、「正しい日本語」が使われているかどうか、「正しい書式」に従っているかどうか、「正しい順序」で書かれているかどうか、「易しくて分かりやすい明文」であるかどうか、が大切とのこと。特に「起承転結」に留意が必要とのことである。
■三番目は、心構え。これが大変むつかしい。ある作家は「小説が扱うのは魂の問題。正面切って対峙(たいじ)して、孤独の海で溺れる寸前まで努力を集中する」必要があると言う。ボクにそこまでやれる自信はないし、仮にやれた時には多分そのまま溺れてしまうだろうと思った。また、その作家は「社会に衝撃を与えてやろうという意図に基づく構成や執筆などは初めから無意味なものである。そのような衝撃は人の精神に何の影響も与えないし、ましてや新しい眼が開かれる訳でもなければ、人生の新しい方向付けがなされる訳でもない」と言っていた。むつかしい言い回しだが、要するに、「格好をつけようと思っちゃいかんよ」ということだと、ボクは解釈した。別の作家は、「とにかく悩み事に向って書く。悩み事を充足するか通過するために読んだり書いたりすると思えばいい」と言っていた。一見分かりやすいようだが、ボクには、どうやって悩み事に向えばいいのかが分からない。また、「胡散(うさん)臭さと悪の匂いがつきまとう感じが物語を作っていく基本」だと言われても、確かに格好いい視点だけど、ボクには到底出来そうもない。さらに別の作家は、「人間は誰でも、忘れることの出来ない場面や心に刻み込まれた情景を持っている。そういう場面や情景は小説を書く上で生きてくる」と言っていた。(そうか、自分の記憶をきっちり整理することから始めればいいんだ)と、ボクは思った。しかし、「物語の筋だけ作るのではなく、物語の本質に迫る」つもりでなくちゃいけないし、「目鼻立ちがはっきりとしていて、風土の匂いがする文章」を書くことや「人間の内側を描くために、外部にこだわっている視線」を持つことも大切だとのことだった。それに加えて、「誇張をまじえた線描(せんびょう)のようなユーモラスな描写の中でこそ登場人物が躍動する」と聴いても、「微妙な屈折を明快な表現で存分に伝えよう」と言われても、そんな高度なテクニックがボクにあるはずがない。そんな迷いの中で、「リラックスして書き続ける。自分の実力に従ってゆっくりと書き続けて少しずつ確実に腕を上げていく。とにかく毎日書き続ける」ことが大切だという言葉を眼にして、ボクは勇気づけられた。
ようやく頭の整理が出来たボクは書き直しすることを決め、その後約一年をかけて仕上げたのが、去年の十二月にやっと出版の運びとなった『ストップ・オーバー』(途中下車という意味)である。四百字詰め原稿用紙換算で一千枚を超えていた草稿は、担当してくれた編集者のB氏から「普遍性」を考慮した様々なアドバイスを得て、最終的に四百八十枚の作品になった。出来栄えはともかく、当初の目的の一つ、「亡くなった息子へのレクイエムにしたい」という思いは達成できたと思っている。あとは、この本が出来るだけ多くの人の目に触れて、「息子と同じ道を辿る若者が二度と出てこないよう社会に警鐘を鳴らす」結果になることを願うばかりである。
処女作の『ストップ・オーバー』を仕上げていく過程で、ボクは多くのことを学んだ。
何をするにも人間、必ず誰かに助けられている。己一人でやり遂げたなどと思うのは大きな勘違いだと思い知った。じゃ、少しはまともな人間になれたかというと、偏屈と我が儘は相変わらず直らない。ボクのような亭主を持った女房殿はつくづく不幸だ、と殊勝にも反省した。が、改めて女房殿の表情や態度をつらつら眺めて見るに、薄幸の女というイメージはないから、(多分、ボクにもどこか善いところがあるんだろう)と勝手に思って、偏屈と我が儘はこれまで通りに貫くことにした。
文章を綴っていくのに、何よりも難渋〔なんじゅう=苦しむこと〕したのは、主人公の青年・広中純の心の様相を推量する作業だった。彼のモデルはボクの息子である。思索を重ねれば重ねるほど、息子の真実をほんの少ししか知らなかった父親の姿が明らかになっていく。素っ裸の自分が見えてくる……。それが苦しい。ボクは七転八倒した。
「ああ、これだったんだ、あの子がオヤジの俺に訴えていたのは……」
そう悟るまで三ヶ月余りを要した。息子はこの世を去る最後の最後までボクを気遣ってくれていたんだと思って涙が出た。(これじゃどっちが親だか分かんないじゃないか)と、己の至らなさに悔し涙が止まらなかった。でも息子のお陰でボクの魂は解放されたと思う。
作詞家から作家に転身して直木賞をとった『なかにし礼』さんがテレビのワイドショーでコメントしていた「小説を書くというのは魂を解放することに他ならない」という言葉が、今もズシンとボクの心の中に突き刺さっている。
息子の遺志に報いるために、ボクは小説を書き続けなければならない。それが今のボクの偽らざる心境である。どんなものが書けるのか、他人様にちゃんと読んでもらえるものが書けるかどうか、自信はないけど、ボクはこれからも小説を書き続けていくつもりだ。
[平成十六年五月]
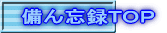
|