
都筑大介 ぐうたら備ん忘録
その九
渋くて可愛いジジイになるぞ!
『都筑大介ホームページ』を立ち上げてちょうど一年が経った。
都筑本人は、数え年で六十一の『還暦(かんれき)』を迎えるまでいよいよ一年を切り、いわば日々カウントダウン状態に入った。
還暦は長寿を祝う最初の賀寿(=祝齢)で『華甲(かこう)』ともいう。華の字が六つの「十」と「一」に分解でき、十二支の最初が「甲子(きのえね)」であることから、そう呼ばれている。
次に訪れる賀寿は数え年七十歳の『古希(こき)』である。この呼び方は中国の詩聖・杜甫の一説「人生七十古来稀なり」からきているのだが、あとは他愛のない形あわせと字あそびが続くから、先の華甲もそうだが、割合近年になって、多分江戸時代につくられた呼び方に相違ないとボクは思っている。
七十七歳の『喜寿(きじゅ)』は喜の草字体が七十七と読めるからであり、八十一歳の『傘寿(さんじゅ)』も傘の略字が八十と読める。
続く八十八歳の『米寿(べいじゅ)』は米の字が八と十と八に分解できし、九十歳の『卒寿(そつじゅ)』も卒の俗字である卆が九と十に分けられる。九十九歳の『白寿(はくじゅ)』は百から一を引くと白になるからというのだからダジャレっぽい。そして賀寿の締めくくりは百歳の『上寿(じょうじゅ)』である。てっきり大願成就の成就(じょうじゅ)をもじったに違いないと思ったが、これは寿命の長い中でも最上位のことだった。しかし、今よりずっと前は八十歳のことを上寿と言ったらしい。
ボクらのご先祖さまたちは、長寿を下寿・中寿・上寿の三段階に分けて、六十歳・七十歳・八十歳あたりをそう呼び習わしたようだ。が、今では六十歳・八十歳・百歳という三段階になっているというのが広辞苑の解釈だ。
「おいおい、都筑。のっけから歳の話ばかりして……。お前、頭がどうかしちまったんじゃないのか?」
そう呼びかけている悪友たちの声が四方八方から聞こえる。
「案ずるでない、友よ。都筑はまだ惚けてはおらんし、狂ってもおらんよ。至って健康じゃわい」
ボクは心の中で皆にそう返答をしたのだが、歳のことを考えていたせいで言葉遣いがジジ臭くなってしまった。
実は、いつもの癖でちょいと横道に逸れたけれど、珍しくボクは自分の今後のことを考えていたのである。
還暦というのは暦を元に還すこと。つまり来年ボクはゼロ歳から再出発することになる。新しい人生が始まるわけだ。
それでボクは、「さてはて新出発を控えているこの一年に、俺は何を為すべきだろうか?」と、柄にもなく真面目に考えはじめてすぐに脱線してしまったという次第である。
「もうじき還暦か。しかし、まだまだ先が長いなあ」
 先月末に満五十九歳の誕生日を迎えたボクは、しこたま呑んだ日本酒に酩酊し、朦朧としている頭でそう考えていた。なぜなら、誰になんと言われようと、たとえ周囲から疎まれても、ボクは九十一歳まで生きるつもりなのだ。 先月末に満五十九歳の誕生日を迎えたボクは、しこたま呑んだ日本酒に酩酊し、朦朧としている頭でそう考えていた。なぜなら、誰になんと言われようと、たとえ周囲から疎まれても、ボクは九十一歳まで生きるつもりなのだ。
ボクの父は、ボクが四歳の時に三十二歳の若さで病没した。が、祖父と祖母は、没年こそ違ったが、ともに満九十一歳で大往生した。ボクが受け継いでいるDNAは、その長生きDNAだとボクは確信している。だから短くても九十一までは生きられると思っている。
しかし、そのことを前提にすると「あと三十二年」もある。ボクが長年サラリーマンをしていたといっても、結構忙しかったその会社勤めは二十八年間に過ぎない。
となると大変である。のんべんだらりと生きていると、有り余る時間と暇にまみれて、今は「認知症」と呼び方が替わった昔の「痴呆症」にきっとなる。
ボクの場合、肉体的健康については、「一病息災(そくさい)」というように、幸いにして?、唯一の病として糖尿病を持っているから無茶は出来ないし、しない。だから、まずは心配ない。あとは頭脳を健康に保つことだが、多分、下手な文章を書き続けることが有益であるはずだ。そして、これまた幸いに、書きたい題材とアイデアが「創作ヒント帖」という極めてダサイ名前をつけたノート六冊に沢山詰まっている。遅筆(ちひつ)と筆力不足のせいでなかなか作品としてまとまらないが、登場人物の設定と筋書きの推敲(すいこう)に時間をかけて一気に書き上げる習性さえ身に着けば、少なくても一年に二作品ぐらいは仕上げられる。
(するてぇと、単純計算で、死ぬまでに六十二作品を書き上げることが出来るなあ。運がよけりゃ、そのうち二つや三つは何かの受賞作品になるぞ、きっと……。しかしまてよ、賞をもらうと忙しくなるらしい。俺、横着もんだから、そいつは困るなあ)
とまあ、能天気に「取らぬタヌキの皮算用」をしながら、ボクは執筆活動を続ける決意を新たにした。
それともう一つ、昔流の下寿(六十代)の間は「もっと渋く」、中寿(七十代)になったら「矍鑠(かくしゃく)として」、上寿(八十代)を迎えたら「可愛く」生きようと、とりあえず心に決めた。
残るは「スケベ心」だが……。ま、そのうち穏やかになるだろう。
[平成十七年四月]
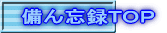
|